歯科では無断キャンセルや当日キャンセルをきっかけに、治療途中のまま患者が離脱してしまうケースもあります。今まで通院していた患者が急にキャンセルして治療をやめてしまうのには以下のような理由があります。
- 痛みがなくなり、治療の必要性を感じなくなった
- 治療の説明が少なく、医院に対し不信感がある
- 歯科医の対応に恐怖を感じる
- 治療に痛みや恐怖を感じる
- 費用が支払えなくなった
- 仕事などの関係で時間が合わなくなった など
歯科のキャンセル対策は一般的なものに加え、患者とコミュニケーションを重ね信頼関係を構築することが何よりも重要です。
この記事では、無断キャンセルを減らし常連を獲得するキャンセル対策とキャンセル料を設定した場合の料金や注意点について紹介します。
無断キャンセル率を減らし常連を増やすキャンセル対策

ここでは、無断キャンセルや途中離脱してしまう人を減らし、常連客を増やすキャンセル対策について紹介します。
治療の必要性と計画に対する具体的な説明
治療計画について、「歯を削って詰め物を詰めていく」と口頭でざっくりとした説明のみで終わらせていませんか。簡単な虫歯の治療であっても、完治に向けてどのような治療計画で進めて行くのか、スケジュールと共に説明することが重要です。
終わりの見えない治療を続けることは通院へのモチベーションを下げますし、歯科への不信感にもつながります。
具体的には、
- 何回目にどのような治療をするのか
- なぜその治療が必要なのか
- 最短と最長で完治までにどの程度かかりそうか
- 費用はどのくらいかかりそうか など
を明確に説明するようにしましょう。また、治療計画を書面にまとめ、随時治療開始にどこまで進んだかを一緒に確認し、完治に近づいていることを患者に実感させてあげるなどの対応も通院のモチベーション維持に役立ちます。
確実に完治へ進んでいく実感は、担当医や医院への信頼感を高める効果も期待できるでしょう。
現在の状態や治療状況を目に見える形にして提示
歯の状態は患者から見えないことが多いため、虫歯に対し痛みが少ないと症状が軽いと思いついサボってしまう人もいます。
そのため、レントゲンだけではなく通常のカラー写真なども利用して、虫歯の状況を見せておくのも重要です。実際に虫歯の箇所を見ることで治療意欲を高めることができます。
治療中断で発生するリスクの説明
歯科の患者の中には、予約のキャンセルをきっかけにそのまま治療を離脱してしまう人も珍しくありません。痛みがない、生活に支障がなくなったと自分で勝手に判断して治療をやめてしまいます。
予約のキャンセルを減らし、継続的に通院してもらうにはキャンセルポリシーを提示する際、中断した場合のリスクについてしっかり説明しておく必要があります。
治療を中断することで、今の歯の状態がどのように悪くなるのか(虫歯が進行し歯を残せなくなる など)を具体的に説明しましょう。
繰り返す無断キャンセルに対するペナルティの設定
無断キャンセルや当日キャンセルを繰り替えさせないためには、ペナルティの設定もおすすめです。
例えば、「無断キャンセルが2回以上続く場合、予約しても緊急処置しかできない」といった治療の制限や、「無断キャンセルが2回以上繰り返される場合、当日予約しか受け付けられない」などの予約の制限が考えられます。
そうすることで、無断キャンセルを行う患者に振り回されずに済みますし、売り上げに与える影響を最小限に抑えることが可能です。
ペナルティを設定する際は、トラブルを回避するためにも口頭で説明した後に書面上でペナルティへの同意をもらうようにしましょう。
勤務先など個人情報の確保
初診で患者の個人情報を取得しますが、キャンセル料の設定を検討している歯科では勤務先の情報をもらっておくことをおすすめします。
無断キャンセルに対しキャンセル料を請求しても拒否されるケースがほとんどです。そういった場合に勤務先の情報をもらっていれば、最終手段として会社の住所で督促状をおくることができます。
予約前日・当日のリマインド
歯科への通院はたいてい週に1回程度で、予約が集中する医院や治療の内容によっては2週間以上あいてしまうこともあります。
ほとんどの人は忘れないように手帳に書き込んだり対策をしますが、それでも2週間以上あいてしまうと忘れてしまう人もいるでしょう。うっかり無断キャンセルさせないためにも来院を促すリマインドメールや電話は効果的です。
キャンセルポリシーの作成と同意
無断キャンセルを減らすには、キャンセルポリシーの作成と提示、口頭での説明が重要です。キャンセルポリシーの内容は医院ごとに異なりますが、最低でも以下の項目は記載しておきましょう。
- キャンセルする場合の手続き方法
- キャンセルした場合に発生する虫歯の状況悪化などに対する免責事項
- 無断キャンセルした時のペナルティ
- 当日キャンセル可能な特例(体温が37℃を超える場合、自然災害により来院が難しい場合などです)
- キャンセル料が発生するタイミングとキャンセル料
- キャンセル料の支払いがない場合の対処法(法的手段をとる可能性がある、勤務先へ督促状が届く可能性がある)
このような項目を設けた上で、同意してもらうようにしましょう。万が一、キャンセルに関してトラブルが発生した際に証拠として不利な状況に追い込まれることを回避できます。
無断キャンセルに対するキャンセル料の設定
ほとんどの歯科では設定されていませんが、キャンセル料を設定し請求することは可能です。
低額でもキャンセル料を設定しておくことで、治療意識の低い患者を来院しにくくさせ、患者の質を上げることができます。
ただ、キャンセル料が設定されていることで、体調が悪い人も無理して来院してしまい、院内感染が起きるリスクもあります。キャンセル料の支払いが不要な特例を設け、通院しやすい体制をつくることが重要です。

歯科でのキャンセル料の決め方と上限

キャンセル料は消費者契約法で「キャンセルで生じた平均的な損害額」と上限が定められています。
歯科の場合、受けているサービスや保険の対象なのか対象外かで大幅に金額が変わってしまうため、上限は同じ治療を行っている人の平均的な客単価から割り出すことになるでしょう。
患者によって治療時間も異なるため、安心できる金額を算出したい場合は、自分で計算せず弁護士に相談することをおすすめします。
また、キャンセル料は上限を超えなければ安い分には問題ないので、低額な料金を一律で設定しておくのも1つの方法です。例えば、一律500円に設定しておけば患者としても支払いに抵抗が少ない上に、上限を越すリスクを回避できます。
なお、転用のできない銀歯などについては、キャンセルに対して発生する損害になるため、患者に対し作成費用などを請求することが可能です。
歯科がキャンセル料を回収するなら事前決済できるプリチェックスがおすすめ

対策としてキャンセル料の設定や請求は効果的と説明しましたが、キャンセルが発生した後に請求しようと思うと費用がかかる上に回収できないリスクがあります。
ここでは、確実に回収できる方法とそれを実現するプリチェックスについて紹介します。
キャンセル料を回収するなら事前決済がおすすめ
プリチェックスは事前決済やリマインド、クーポンの発見など支払いから来院促進まで一括で行える、事前決済型のキャンセル対策ツールです。
ネットや電話で受けた予約情報をガイドに沿って入力し、患者に送り、決済情報を入力してもらうだけでデポジットをもらうことができます。
予約サイトと連携していない分、初診の人や仮歯を詰めた人、過去に無断キャンセルした人とピンポイントでプリチェックスを送ることも可能です。
患者が予約通り来院した場合は、診察料からデポジットで受け取った金額を差し引き清算します。一方、当日キャンセルされた場合、24時間後にデポジットが支払われます。
キャンセル料を請求すると、いつまでも支払われない、なかなか回収できないといった不安と戦うことになりますが、プリチェックスであればそのような不安が一切ありません。
歯科がプリチェックスを利用するメリット
無断キャンセル対策では業種が限定されていることもありますが、プリチェックスでは歯科を含め幅広い業種で利用することが可能です。
事前にキャンセル料を受け取っているので、当日キャンセルが発生した後に時間を削って請求手続きをする必要がありません。また、自動的に支払われるので患者と交渉したり直接やり取りを行う必要がないためストレスを感じずに、キャンセル料を回収できます。
また、弁護士などにキャンセル料の回収を依頼すると回収額の3割以上が手数料として請求され費用倒れになったり、手元に入るお金が少なくなります。しかし、プリチェックスであれば手数料は決済額の10%のみ。そのため、費用を抑えた上で確実なキャンセル料の回収が可能です。
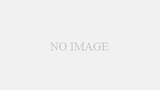
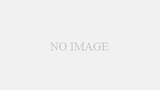
プリチェックス導入までの流れ
プリチェックスの導入には特別な機械が必要ないため、簡単な4ステップで利用を開始できます。導入まで最短で7営業日なので、繁忙期に備えすぐに導入も可能です。
まとめ
歯科の無断キャンセルを減らすには、キャンセルポリシーやキャンセル料に関する張り紙をしておくだけでは行けません。
院内でどのような説明をしているのか、どの程度患者とコミュニケーションが取れているのかを見直し、患者に通院意欲や治療への意欲を高めてもらう対応が必要です。
また、今までしっかり通院してきたのに無断キャンセルしてしまった人に対しては、医院側から「今日は体調が悪いのでしょうか?連絡がないので心配しています」とフォローしてあげることが重要です。
しっかり通院している人ほど、一度キャンセルしてしまうと罪悪感から通院を再開できず、離脱してしまうことがあります。フォローしてあげることで、離脱させず通院を再開させることができるでしょう。
このような対応の上で、よりしっかりと無断キャンセルへの対策を検討するのであれば、プリチェックスのような事前決済ツールを導入することをおすすめします。
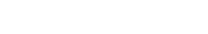



コメント